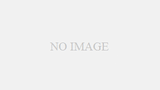SNSや掲示板、口コミサイトなどで突然、自社への誹謗中傷が投稿されたとき、企業は一刻も早く冷静かつ的確な初動対応を取る必要があります。初動を誤ると、情報は瞬く間に拡散され、企業の信用やブランドイメージに大きなダメージを与える可能性もあります。本記事では、誹謗中傷の被害に直面した企業がまず取るべき行動や体制整備のポイントを、実務目線でわかりやすく解説します。
まずやるべきは「証拠の保存」と「被害の全体把握」
企業がネット上で誹謗中傷の被害に遭遇した場合、真っ先に行うべきなのは証拠の保存と状況の把握です。投稿が拡散するほど削除や修正が難しくなるだけでなく、法的措置を取るうえでも「いつ・どこに・何が」書かれていたのかを正確に記録することが非常に重要となります。
まずは、問題となっている投稿のURL、投稿日時、スクリーンショット、投稿内容全文を保存します。可能であれば、投稿が行われた前後の文脈やコメント、引用元なども記録しておくと、後の調査や裁判対応で有利になります。
次に、被害の規模を把握することも不可欠です。「どれくらい拡散されているのか」「どの媒体に転載されているか」「顧客や取引先から問い合わせが来ているか」といった影響範囲の確認を行います。GoogleやSNS検索、掲示板巡回、アラートツールの活用など、可能な限りの情報収集を行い、全体像をつかんでおきましょう。
この段階では、感情的に反応してしまうことが最も危険です。誤った対応をとれば二次炎上の原因にもなりかねません。あくまで“証拠保全”と“情報の整理”を冷静に進めることが、すべての初動対応の基盤となります。
社内で混乱を防ぐための指揮系統と対応チームの設置
誹謗中傷が社内で発覚したときにありがちなのが、複数部署がそれぞれ独自の判断で動き始め、結果として混乱や情報の錯綜が起きてしまうケースです。こうした事態を避けるためには、明確な指揮系統の構築と専任の対応チームの設置が重要です。
まず、社内で危機管理の主導権を握る責任者(たとえば経営陣、広報責任者、法務担当など)を明確に定め、その人物を中心とした対応チームを結成します。このチームが、情報の収集・方針の決定・対外的な対応の窓口などを一元的に担う体制をつくります。
加えて、各部署への「勝手な発信の禁止」も徹底します。とくにSNSや顧客対応の現場では、感情的なコメントや“軽い気持ちでの反論”が状況を悪化させる火種になります。社内の誰がどこまでの権限を持って発言してよいのか、明確なルールを設けましょう。
また、初動対応のフローや対応マニュアルを平時から用意しておくことも有効です。実際に誹謗中傷が起きたときに初めて動き出すのではなく、「誰が、いつ、どんな情報を、どのように処理するか」をあらかじめ想定しておくことで、企業全体の対応力が格段に高まります。
初動時の社内体制は、まさに“企業の危機対応力”そのものを反映します。全員が一丸となって冷静に動ける組織こそ、信頼を守れる企業といえるでしょう。
投稿の性質に応じた初期判断と専門家への相談の目安
誹謗中傷とひと口に言っても、内容によって対応方法は大きく異なります。たとえば、「明らかに虚偽の事実が書かれている場合」「侮辱的な表現がある場合」「プライバシーが侵害されている場合」などは、法的な対処が必要になる可能性が高いため、早い段階で専門家に相談することが望ましいです。
逆に、「サービスに対する不満」「感想に近い表現」「誤解に基づく発言」などの場合は、法的な削除は難しいことも多く、広報対応や情報発信によって印象を修正する戦略が求められます。どちらに該当するかを早急に見極めるためにも、初期段階での専門家の目が重要になります。
まず相談先として考えたいのが**弁護士(IT・風評分野に強い)**です。投稿内容が名誉毀損や業務妨害に該当するかどうか、削除請求や発信者情報の開示請求が可能かなど、法的な観点から判断してもらうことができます。
また、逆SEOやモニタリング、サジェスト対策などの技術的対応を得意とするIT専門企業にも早めに相談するとよいでしょう。すでに投稿が拡散していたり、検索結果に悪影響が出ていたりする場合には、専門的な対策が必要になります。
どの専門家に相談すべきか迷う場合でも、まずは初期の証拠を持って無料相談や問い合わせをしてみることで、自社にとって最適な方針が見えてきます。
対外発信は慎重に!企業イメージを守る情報管理術
初動対応において見落とされがちなのが、外部への発信の仕方です。誤ったメッセージや対応は、炎上を再燃させたり、さらなる誤解を招いたりする原因になります。だからこそ、誹謗中傷発生時の情報管理と対外発信は、特に慎重に行う必要があります。
まず重要なのは、「何も発信しない」という判断も選択肢に含まれるということです。すべての事案が説明責任を伴うわけではありません。内容や影響範囲によっては、発言することでかえって注目が集まり、炎上が広がってしまう場合もあります。
一方で、影響が大きく、顧客や取引先に不安が広がるようなケースでは、タイミングを見て公式声明を出す必要があります。その際は、事実確認中であることや、被害を深刻に受け止めている姿勢を丁寧に伝えることで、誠実な企業イメージを守ることができます。
また、投稿に対して「直接返信する」ことは非常に慎重になるべきです。SNSでの返信や反論は、文面ひとつで批判の的になるリスクがあります。できれば広報や法務のチェックを通し、内容や言葉選びを徹底することが望ましいです。
“黙っていてもダメ、余計に反論しても危険”というのが、誹謗中傷対応における情報発信の難しさです。だからこそ、事実を正しく伝えるための冷静な判断力とメディア戦略が、企業の信頼を守る最後の砦となります。
まとめ
誹謗中傷は一瞬で企業の信用を揺るがすリスクを持っていますが、初動対応次第で被害を最小限に抑えることは十分に可能です。まずは証拠を正確に保全し、状況を冷静に整理。社内の対応体制を整えたうえで、投稿内容に応じて法的・技術的な専門家と連携を図りましょう。情報発信にも慎重な判断が求められるなか、企業の信頼を守るカギは、慌てず正しく動ける「初動の力」にあるのです。