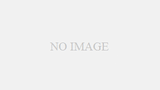中小企業にとって、ひとたび発生した風評被害は経営に直結する深刻なリスクです。たとえ一部の誤解や虚偽の書き込みであっても、取引先の信頼や顧客離れを招きかねません。しかし、正しい対応を知っていれば、拡大を防ぎ企業の信頼を守ることが可能です。本記事では、風評被害に直面した際に中小企業が取るべき対応を、段階的かつ実践的なマニュアル形式で解説します。
被害拡大を防ぐために最初にやるべき初動対応とは
中小企業が風評被害に直面したとき、最も重要なのは「初動対応の速さ」と「冷静な状況把握」です。SNSや口コミサイトにネガティブな情報が投稿されていたとしても、感情的に反応してしまうと、かえって炎上を招くリスクがあります。まずは投稿内容を客観的に確認し、どのような経路で拡散しているのか、どの程度影響が出ているのかを把握することが第一歩です。
初動で確認すべきポイントとしては、「発信元(個人・匿名)」「拡散状況(SNS・検索エンジン)」「内容の信憑性(虚偽・誤解・一部事実)」の3点です。この時点で、法的リスクや明確な虚偽が含まれるかどうかを見極め、対応方針を定めていきます。
次に、社内での情報共有も極めて重要です。経営者や広報担当、現場責任者など関係者に状況を伝え、誰が対応を担うのかを明確にします。たとえ少人数の組織であっても、「全員が情報を共有し、勝手な対応をしない」ことが被害拡大を防ぐカギになります。
また、SNSなどでユーザーから直接問い合わせがあった場合には、誠実かつ冷静に対応し、事実を説明する姿勢が求められます。無視したり否定的な態度を取ったりすると、さらなる誤解を招きかねません。誤情報であれば「事実と異なる内容が確認されており、現在調査中です」といった表現で、慎重に返答することが適切です。
初動対応は、その後の企業の信頼回復に大きく関わります。焦らず、正しく状況を見極めたうえで、次の行動に進むことが肝心です。
事実確認から削除依頼まで、情報整理と交渉の流れ
風評被害への対応は、ただ削除を求めるだけでは解決しません。まず行うべきは、投稿内容の「事実確認と記録」です。内容が事実かどうかを確認し、事実であればどのような改善策をとってきたか、虚偽であればその根拠を明確に整理します。そのうえで、画面キャプチャやURL、投稿日時などを保存し、証拠を残しておくことが重要です。
続いて行うのが「削除依頼」の手続きです。Google検索に関しては、検索結果からの削除申請が可能ですし、レビューサイトやSNSの場合は、それぞれの運営会社にガイドライン違反を理由として申請を行います。たとえば、Googleビジネスプロフィールであれば、「不適切なレビュー報告」から削除依頼が可能です。
ただし、全ての削除申請が通るわけではありません。特に匿名掲示板などでは運営側の対応が遅かったり、削除に消極的であったりすることも多く、根気が必要になります。このような場合には、法的措置(発信者情報開示請求・損害賠償請求など)を視野に入れることも一つの選択肢です。
また、内容によっては直接の“交渉”によって問題解決できる場合もあります。たとえば、実際にサービスを利用した顧客が不満を投稿しているケースでは、真摯に謝罪し、対応を提示することで、投稿者が自主的に削除・修正してくれることもあります。
つまり、事実確認 → 証拠保全 → 削除依頼 or 交渉 or 法的対応、という流れを踏むことで、無駄のない対応が可能になります。どのステップも丁寧かつ正確に進めることが、中小企業にとっての信頼回復に直結します。
公的機関・専門家・外部サービスの適切な活用法
風評被害の対応においては、社内だけでの対応に限界があることも多々あります。特に中小企業では、広報や法務の専門部署がなく、対応に悩むケースも少なくありません。そんなときには、外部の専門機関や専門家の力を活用することが大切です。
まず、公的な相談窓口として活用できるのが「法務局(人権相談窓口)」や「総務省(違法・有害情報相談)」などです。ネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害に該当する場合、初期相談や削除依頼の手順についてアドバイスを受けることができます。
次に、インターネットの風評対策を専門とする業者への依頼も有効です。いわゆる「逆SEO」や「サジェスト対策」などを代行してくれる企業に依頼することで、自社にとって好ましい情報を検索上位に表示させ、ネガティブな情報の露出を抑えることができます。これにより、検索経由での印象悪化を防ぐことが可能になります。
また、弁護士と連携することで、発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置にも対応できます。内容が明らかに名誉毀損に該当するような場合は、早期に法的対応を視野に入れることが望ましいです。
外部の専門家と連携する際には、「費用」「期間」「成果の見込み」などを事前に確認したうえで、目的に応じた最適なサポートを選ぶことが大切です。すべてを自力で抱え込まず、信頼できる専門家と協力して進めることが、最終的な被害抑止につながります。
再発を防ぐために整備すべき社内体制と情報発信戦略
風評被害に対する対応は、その場限りでは終わりません。むしろ重要なのは、「再発を防ぐための体制づくり」です。特に中小企業においては、限られた人員のなかでリスクに備えるために、“シンプルかつ効果的な仕組み”を整備する必要があります。
まず基本となるのが、「モニタリング体制」の確立です。月に1回でも、自社名やブランド名をGoogle検索し、サジェストやレビューをチェックするだけでも初期兆候を掴むことができます。必要に応じて、GoogleアラートやSNS検索ツールを活用すれば、自社に関する投稿を自動で検知することも可能です。
次に、「広報対応のルール化」も重要です。たとえば、SNSで質問やクレームがあった場合の返信テンプレートを用意したり、外部発信を行う際の言葉遣いやタイミングに関するガイドラインを定めたりすることで、不用意な発信による炎上リスクを減らすことができます。
さらに、日頃から「ポジティブな情報発信」を続けることで、検索エンジン上の印象を改善・維持することができます。お客様の声、地域貢献活動、実績紹介など、信頼を高めるような内容をブログやSNSに継続的に発信していくことで、自然なかたちで風評対策にもなります。
社内教育も忘れてはいけません。社員全体が「ネットの怖さ」や「発信リスク」を理解していることが、未然の防止につながります。風評被害を機に、あらためて組織としての体制を見直すことが、中小企業にとっては大きな成長機会にもなり得るのです。
まとめ
風評被害は、企業規模に関係なく突然発生し、特に中小企業にとっては経営を揺るがす深刻な問題となり得ます。しかし、冷静な初動対応、正しい情報整理、外部支援の活用、そして再発防止の社内体制づくりを整えれば、被害の拡大は抑えられます。何よりも大切なのは、情報社会の今、“起きてから”ではなく“起きる前”から備えるという意識です。風評に強い会社は、信頼される会社へとつながっていきます。